アルマイト皮膜は電気を通す?通さない? “絶縁性”と環境による影響
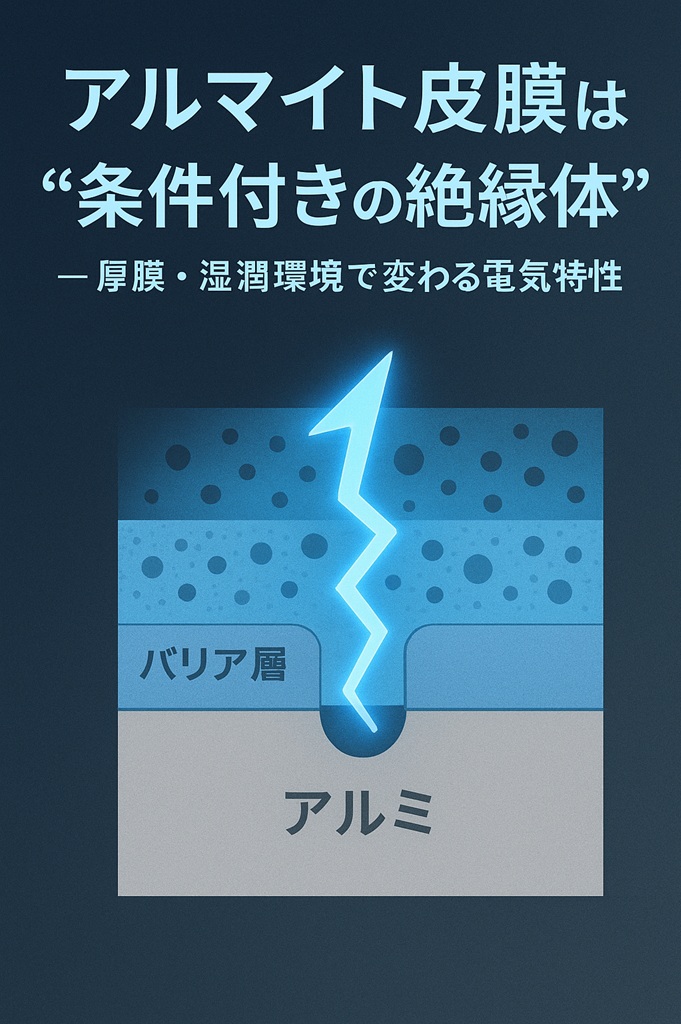
1.アルマイト皮膜の構造と基本特性
アルマイトは、アルミニウムを電解処理することで生成される酸化アルミニウム(Al₂O₃)層です。
皮膜は大きく分けて、次の二層構造で形成されています。
- 多孔質層:微細な孔が無数に存在し、染色や封孔処理を行う部分。
- バリア層:アルミ素地と密着する緻密な層で、厚さは数十ナノメートル程度。
酸化アルミニウムは本来、体積抵抗率が10¹²~10¹⁴ Ω・cmと非常に高く、優れた絶縁性を持っています。
そのため、一般的な電気試験では「導通しない=絶縁体」と判断されます。
2.「絶縁体=完全に電気を通さない」わけではない
⑴厚膜だから安心? 実はそうでもない
アルマイトの絶縁性は膜厚に比例して高くなる傾向がありますが、
「厚膜=完全な絶縁体」とは言い切れません。
環境や条件によってわずかに電流がリークすることがあります。
厚膜ならではの弱点がクラックです。
特に厚膜の硬質アルマイトでは
クラック発生のリスクは高まります。
微細なクラックが入りわずかに母材が露出した部位では
完全に絶縁性が失われます。
反対に薄膜(5μm以下)の場合は、
皮膜自体が薄く電流が通りやすい傾向にあります。
⑵未封孔では湿潤環境で抵抗値が低下する
アルマイト皮膜の多孔質構造の封孔が不十分な状態、
特に硬度重視で封孔をしていない硬質アルマイト等は、
湿気を吸収する事があります。
高湿度・結露環境では、
孔内部に水分や電解質が容易に侵入し、
電気の通り道ができる事があります。
その結果、乾燥環境で10¹²Ω・cmあった抵抗値が、
湿潤条件では大きく低下することもあります。
この現象は、屋外機器や高湿度環境に曝される製品の
絶縁信頼性を大きく左右する重要な要素です。
⑶絶縁破壊電圧の目安
アルマイト皮膜も絶縁体とはいえ、
一定電圧を超えると絶縁破壊が起こります。
一般的な硬質アルマイトでは、30V/μm前後が目安になります。
(条件や環境による)
たとえば膜厚20μmであれば、
おおよそ600V前後で破壊する可能性があります。
静電気の影響を受けるような装置では、この点も考慮が必要です。
3.導電が必要な場合の対策方法
電子部品やアースポイントなど、通電を必要とする箇所では、
以下のような対策が必要です。
| 方法 | 内容 | 特徴 |
| マスキング処理 | 処理前に接点部をマスキングして素地を露出 | 最も確実でシンプルな方法 |
| 導電アルマイト | SCダイズ®等を採用 | 抵抗値を制御(10⁷~10⁸Ω) |
| 部分研磨・除膜 | 処理後に通電部を機械的に除去 | 小面積で導電を確保したい場合に有効 |
4.まとめ
| 観点 | ポイント |
| 絶縁性の本質 | 酸化アルミ由来の高抵抗体だが、完全絶縁ではない |
| 膜厚による違い | 厚膜でも水分を含めば抵抗値が下がることもある |
| 環境の影響 | 湿潤や高電圧条件で特性が大きく変化する |
| 設計上の注意 | 導電が必要な箇所はマスキングや導電アルマイトで対応 |
アルマイト皮膜は、一般的には「電気を通さない」
優れた絶縁被膜です。
しかしその特性は
膜厚や環境条件によって変化するため、
設計段階で「どの程度の絶縁性が求められるか」を
明確にしておくことが重要です。
特に湿度や結露の影響を受ける環境では、
封孔処理や表面状態を含めた
実使用環境での評価を行うことで、
より安定した絶縁性能を確保できます。
関連記事


