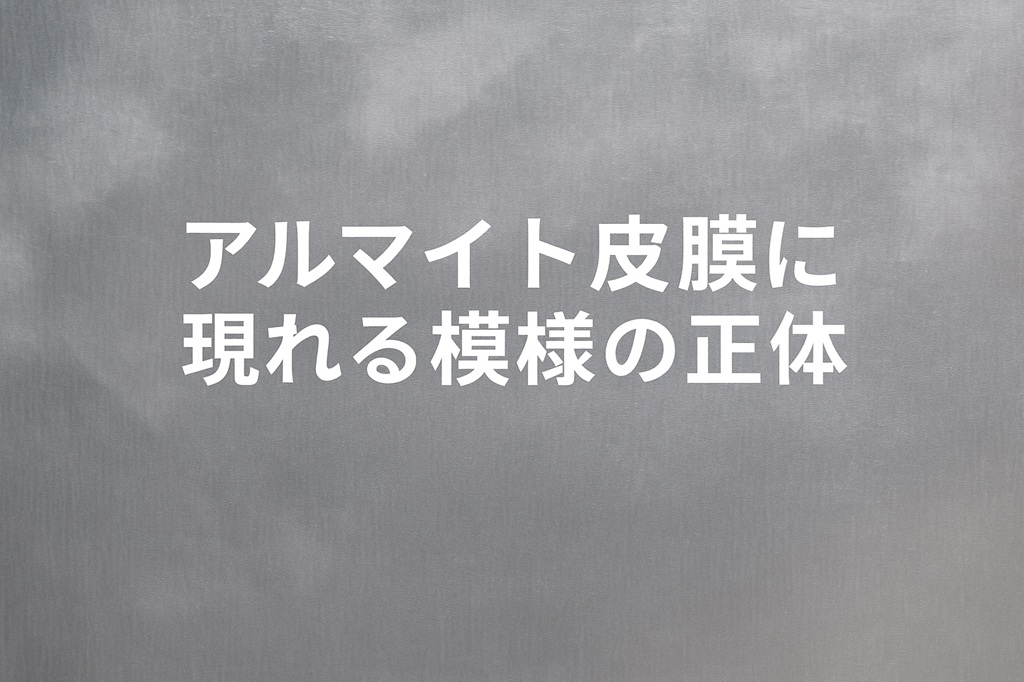
1.模様はどこから生まれる?(素材内部の“地図”を見る)
アルミ材の表面は、一見均一に見えますが、
結晶粒の方向や合金元素の分布がわずかに異なります。
この組織差がアルマイトの電解時に局所的な差となり、
結果として「微妙な光沢差」や「スジ模様」として
外観に現れる事があります。
模様が発生する代表的な3つのパターン
①押出材の流動方向は結晶の流れが残り、縞状模様が出る
②熱処理履歴の差により析出粒子が残り、局所的な皮膜厚差を生む事がある
③合金元素の偏り(例:Si, Cuなど)による電解速度の不均一化
つまり模様とは、素材の履歴が可視化されたものです。
2.前処理・機械加工の影響も無視できない
アルマイト前のエッチングや研磨も模様の発生の原因になります。
機械加工の送り痕が完全に除去できていない場合や、
表面に防錆油が酸化・重合し固着している場合等では、
通常の脱脂工程では完全に除去出来ず
電解反応が局所的に阻害され、「スジ状」「雲状」の模様が強調されることがあります。
また、アルミダイカスト製品など鋳造肌特有の結晶偏析を持つ素材では、
模様の出方がさらに顕著です。
3.ADC12材とMDコートに見る「模様」の現れ方
当社でMDコート処理を行う際、対象となる素材の多くは
アルミダイカスト材(ADC12)です。
アルミダイカスト材のほとんどが、寸法安定性に優れる一方で、
射出成型時の溶湯が流れた跡(湯模様)や偏析ムラ
といった鋳造特有の模様を持つ素材でもあります。
これらは鋳造時の溶湯の流れや
凝固過程や離型剤成分の影響で生じるSiリッチ層やCu濃化部などによるもので、
電解時に局所的に反応速度が異なるため、
皮膜厚や光沢のわずかな差として模様が発現します。
MDコートでは、こうしたアルミダイカスト材特有のばらつきを考慮し、
皮膜形成をできる限り均一化するための調整を行っています。
これにより、偏析の影響を最小限にし、耐食性を向上させています。
4.まとめ
アルマイト皮膜の模様は、
単なる「ムラ」ではなく、素材・加工・電解の履歴が刻まれた記録です。
そのメカニズムを理解し、適切に制御することで、
より美しく・高機能なアルマイト処理を実現できます。



